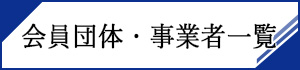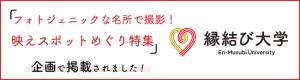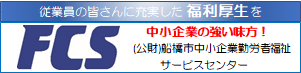第23回千葉県建築文化賞優秀賞受賞

本社(意富比神社)東横の神 榊山麓に新しくご造営された常磐神社のお社です。
おすすめポイント
常盤神社の由来
常磐神社は、江戸時代には「関東一宮両御神社」「関東一宮船橋両社」と本社意富比神社と並び称されていました。
平戸藩主松浦靜山の甲子夜話巻三十一には「神祖の御宮にて官より造らるる処は七ケ所なりと云。日光山、久能山、上野、紅葉山、仙波、世良田、船橋(大神宮の坐す地なり)是なり」と記され、昔は日光山、久能山等の東照宮と同視されていました。
社伝によると、「有徳院様(吉宗公)にも当宮は格別めでたき御宮と上意あらされ候。(略)尊慮にも船橋大神宮は関東一の宮殊更伊勢大神宮との勅号も有之。東照宮様も御鎮座あらせられ候へば、伊勢日光へ参宮相成がたき者は船橋へ参宮いたし候へば、伊勢日光参拝いたし候も同じ」と上意あらせられたと伝わっています。
略 記
天正19年(1591)常磐の御箱という物に開運の旗と陣弓とを添えて家康公本社に納める。
慶長13年(1608)本社遷宮祭の時、家康公は日本武尊の像を作って本社に祀る。
元和8年(1622)秀忠公が家康公の前歯や四将の木像を奉納し、常磐神社を造営する。
寛永16年(1639)家光公が秀忠公の像を納め祀る。
社殿の規模
社殿の大きさは「文政十三年(1830)の頃には本殿は五間四面位、拝殿は六間に五間位あるだろうと、言われていた。周囲には玉垣を廻らしてあったという。」 【成田道の記】
また、 文化11年(1814)の遊歴雑記には、「萱葺の御門ありて扉の上の方には菊の御紋、下の方には葵の御紋と片扉に二ずつ木地の高彫りにして四つ御紋を彫り付けたり、菊の御紋を並べ付けられしは最珍らし。」とありました。
これらの社殿は戊辰の戦火に焼失し再建された社殿は九尺四方の木造瓦葺の小祀でした。この度造営される社殿は本殿間口、三間、奥行二間、高さ二十五尺、唐門間口、一間半、高さ十七尺、彩色漆塗り仕上げとなります。
ご造営相成りました暁には、本殿中央に日本武尊、左に東照宮様と井伊、本多、酒井、榊原の四将を、右に秀忠公に加え、御歴代の将軍家をお祀りいたします。 (原文のまま)
常磐神社と徳川家康公の関係
徳川家康公は日本武尊が、この地に上陸し、大神宮をここに奉祭した縁起を非常に深く信仰し、天正19年11月(1591)常磐の御箱と、開運の旗、陣弓とを添えて本社(意富比神社)に納め、その後慶長13年7月(1608)本社遷宮祭の時、家康公は日本武尊の木像を作って本社に奉納した。ついで元和8年10月(1622)秀忠が家康公の前歯や4将(井伊、本多、酒井、榊原)の木像を奉納、併せて本社東横の神榊山麓に新宮を造営し、これらの木像を新宮に奉斉した。寛永16年9月(1639)家光が秀忠の木像を納めまつった。
この社を常磐神社という訳は、家康公が奉納した箱の名が常磐の箱ということからです。
住所
〒273-0003 千葉県船橋市宮本5-2-1
アクセス
電車でお越しの方へ
- 京成本線 大神宮下駅 徒歩3分
- JR総武線 船橋駅 南口 徒歩15分
お車でお越しの方へ
京葉道路 船橋ICまたは花輪ICから7分
駐車場 無料
(台数に限りがございますので、御参拝には公共交通機関または近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします)
ギャラリー